







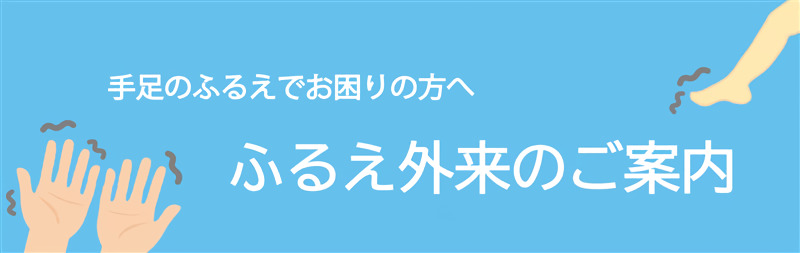
横須賀市の中央に位置する、横須賀市立総合医療センター。
明治より100年以上の歴史を持ち、高い技術力のもとで地域に密着したぬくもりある治療を行っています。
同院の脳神経外科・内科では毎週金曜日に「ふるえ外来」の時間を設け、薬物療法、集束超音波療法(FUS)などを含む治療の選択肢を患者さんに提供しています。
今回は、うわまち病院の脳神経外科でふるえ外来を担当されている東島先生にお話を伺いました。
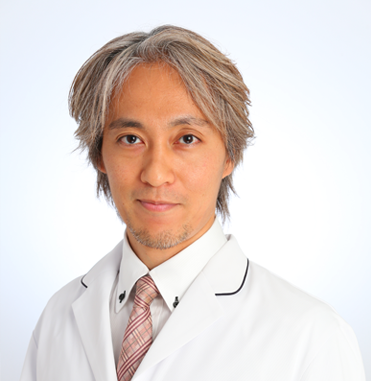
横須賀市立総合医療センター 脳神経外科
ふるえ治療センター センター長
Q脳神経外科のスペシャリストになられたきっかけは何でしたか?
A
一言で言うと、「脳よりも興味がある臓器がなかった」からですね。
もともと、精神科に興味があってたくさん本を読んでいました。
学生時代にフランスのアンリ・モンドール病院*の見学に行く機会があり、その際にニューロスピン(フランス国立研究所)**などの先端施設にも連れて行ってもらいました。
今思えば、当時現地で「脳神経外科ではこういうことができる」「将来こんなことができるようになるかもしれない」とさまざまなお話を聞いたことが、脳神経外科を意識したきっかけだったと思います。
*アンリ・モンドール病院(Henri-Mondor University Hospital):
フランスのパリ郊外にある病院。パーキンソン病などの脳神経疾患に特化した研究で世界的に知られている。
**フランス国立研究所ニューロスピン:
超高磁場MRIについて最先端の研究を行っている施設。
Qふるえの治療について、現在課題だと思われる点は?
A
脳神経外科の先生が不足していることは課題のひとつだと思います。
私自身も後輩を育成していて、若手の方々が脳神経外科という分野に触れる機会が少ないとひしひしと感じます。
若手の方には、たとえばFUS機器を使用した治療を実際に体験してもらえる機会を積極的に作りたいですね。
また、他科の先生方への情報周知も大切です。脳神経外科が扱う内容もそうですが、脳神経疾患への理解もまだまだです。
医師の中でも、「手のふるえを手術して治す」という概念が定着しきれていないところがあると思います。
「そもそも、治るものなのか」から始まって、未知の領域が多い分野ですから、潜在的な患者さんの母数は多いのに情報がなかなか行き届いていないのが現状です。
Qふるえについてこれから発信していくべき情報は何だと思いますか?
A
個人的には、「その治療をしてどうなったか」をやはり見てほしいと思います。患者さんの声ですね。
「〇〇の値が何%改善した」というデータ的なところよりも、「あたたかいお味噌汁が飲めるようになった」など、
患者さんやご家族の方にはこの治療を行うことによりこうなれる、というビジョンの部分をぜひ知っていただきたいです。
医師の自己満足で終わらないために、患者さんができなかったことができるようになって、社会がどう良くなっていくかというのを示していくことが必要だと思います。
Q少しお話は変わりますが・・・先生は麻雀のプロ競技者だと伺ったのですが、これまでの経緯を教えていただけますか?
A
単純に麻雀が好きだったのでプロとして活動していたのですが、公式戦で勝ち上がっているときに手術の連絡が来て退席せざるを得なかったんです。
医師と競技者の両立はこれ以上難しいと感じながら、それでも自分の知識と技術を何らかの形で生かすことができればと思っていました。
そこで、今は麻雀界を学術的な面でバックアップできればと思ってデータ主導の研究をしています。
「サクセスフル・エイジング」という、幸福に歳を取っていきましょうという概念がありますが、
たとえば中国の場合はこの要素で麻雀が上位に入っていました。ガーデニングも効果があるようです。
老化はまず筋肉からはじまり、その後に皮膚、骨の順に進みます。脳は最も歳を取らない臓器なので、脳を使う趣味は高齢化社会に適応しているのではないでしょうか。
Q脳神経外科の医師として、やりがいを感じられる点は?
A
やはり、患者さんが良くなるところが目に見えるという点ですね。これが醍醐味です。
動けなくなる人を増やす延命医療がずっと主流だった中で、脳神経外科治療が発展することにより「動けなくなった人をまた動けるように」する医療の提供
が今後のテーマになると思います。
※本記事は2024年12月執筆当時のものです。